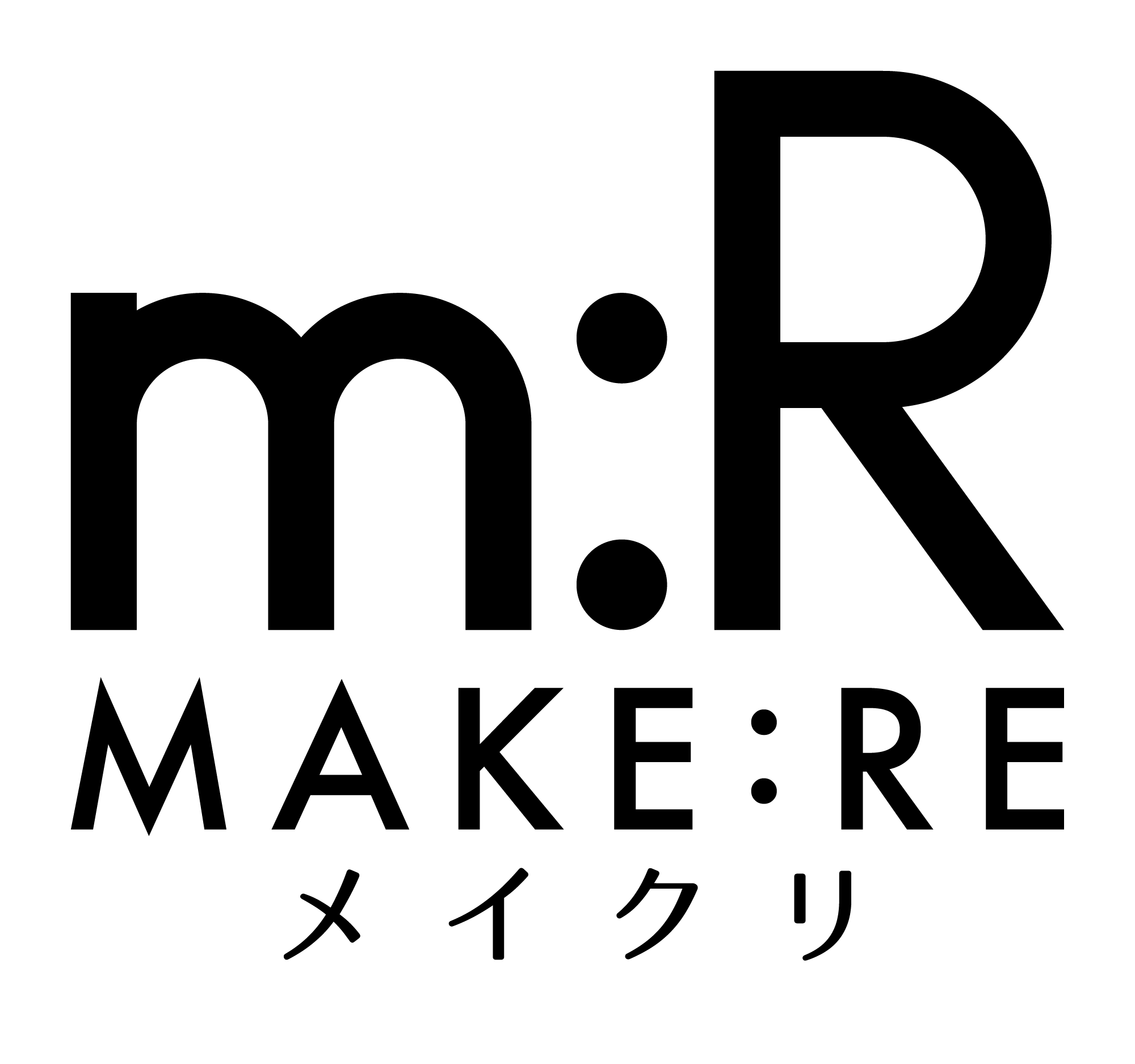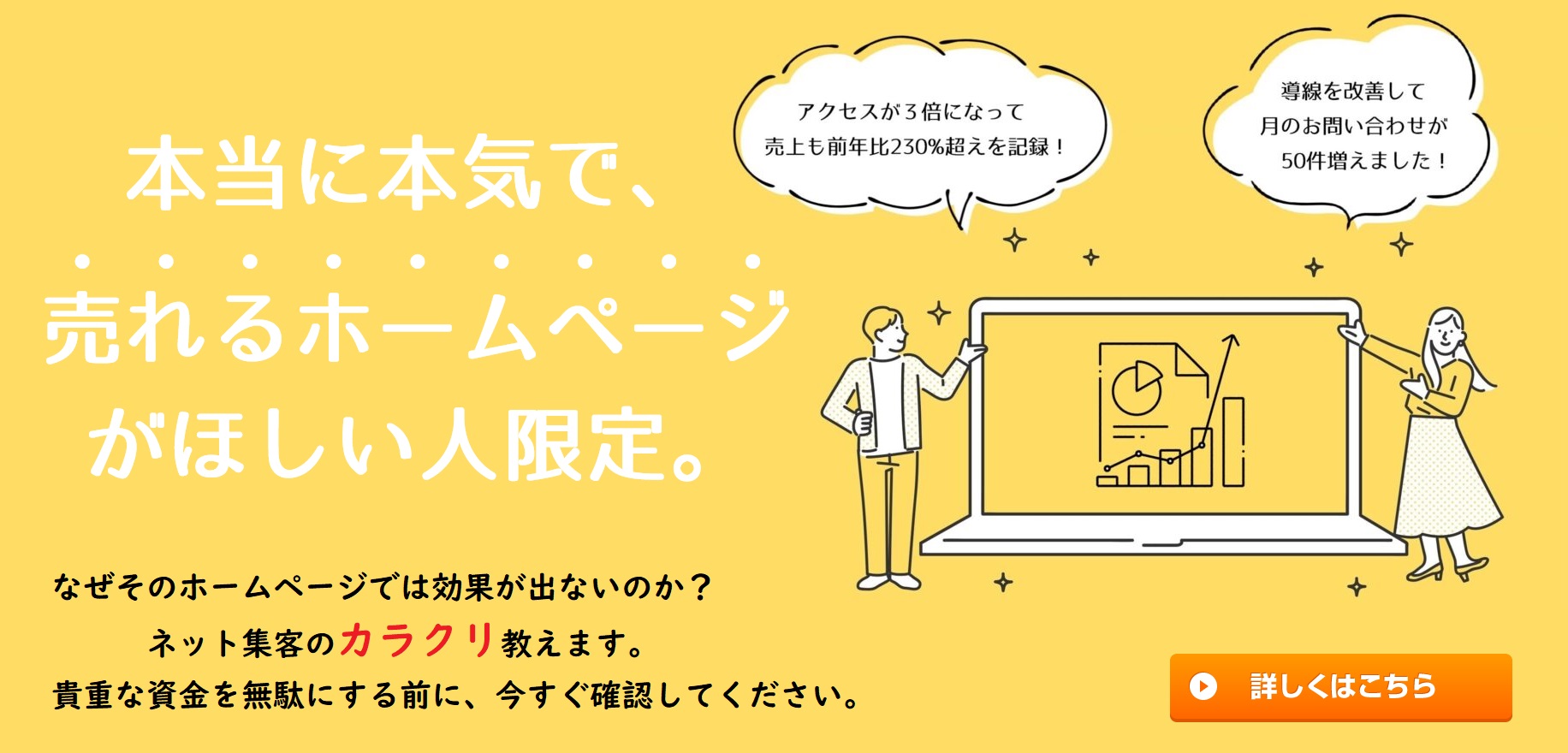2020年12月4日(現地時間12月3日)、Google公式が『December 2020 Core Update』という名称でコアアルゴリズムアップデートの展開を発表しました。
2019年までは概ね三か月周期で行われてきたコアアルゴリズムアップデートですが、2020年は5月のアップデートを最後に音沙汰がなく、「コロナ禍の影響もあるので年内のアップデートは無いのでは?」との見方が強まっていたのですが、大方の予想を裏切り年内最後(になるであろう)アップデートが実施されました。
約2週間ほど続くコアアップデートの展開ですが、今回も例に漏れず12月17日にロールアウト完了の報告がされています。
はたして今回のアップデートはどのような影響があったのでしょうか?
いまだ小規模な変動は続いているものの、ロールアウト完了から数日経って見えてきたものもありますので、簡単に説明していきます。
※コアアルゴリズムアップデートとは?
ちなみに、この記事に興味を持ち読んでいる方はすでにご存じだと思いますが、念のため「そもそもコアアルゴリズムアップデートとは?」について簡単におさらいしておきましょう。
コアアルゴリズムアップデートとは、その名の通りGoogleの検索システムを構成するアルゴリズムの中でも“コア(核)”となるような大規模で重要なアップデートのことです。
Googleの検索順位を決めるアルゴリズムは大小様々なものがあり、それらが複雑に噛み合ってランキング決定しています。その数は200種類以上とも言われていますが、正確な数字な内容は公表されていないために詳細は不明。小さなアルゴリズムの変更や調整は日々行われておりそれに伴う順位の変動も日々起きています。
そんなアルゴリズムの中でも、特に重要で肝となるのがコアアルゴリズムアップデート。
コアアルゴリズムアップデートは年に数回実施されていますが、アルゴリズムの根幹部分に変更を加えるためその影響は非常に広範で大規模なものになります。
そのためもあってか、他のアップデート情報など事後報告が多いGoogleにあって、コアアルゴリズムアップデートは原則事前に告知されています。
今回も先のツイートで紹介したように、ロールアウト前の12月3日とロールアウト完了後の12月17日にアップデートについての報告がありました。
2020年12月コアアルゴリズムアップデートの傾向
ではそんな今回のコアアルゴリズムアップデート、具体的にどのような影響(傾向)があったのでしょうか。
主なポイントは3点になります。
1:大手ドメイン配下のサイトやサブドメインサイトが下落
まず顕著で特徴的だったのが、ドメインパワーにより上昇していたサイトの下落です。
近年、Googleはメディアの信頼性を特に重視し評価してきました。
その信頼性の評価の大きな部分を占めていたのがドメイン全体の強さ(=ドメインパワー)であり、具体的には誰もが知る大企業や大手が運営するメディアかどうか?が重要になりました。
たしかに無名の個人が書くブログ記事よりも、社会的責任も伴う大企業が資金や人的リソースを割いて制作するコンテンツのほうが信頼できる、というのは一理あるでしょう。
Googleとしてもとりあえず大企業のドメインを上位に表示させておけば、たとえそのコンテンツに問題があっても責任を負われるのは大企業であり、Googleにその矛先が向かうことは少なくなります。反対に匿名個人のブログが上位に表示されていて、その内容に問題があれば「こんな内容を上位に表示させるなんてGoogleは何を考えているんだ!」と槍玉に挙げられる可能性も高くなります。
となるとGoogle的にはどちらを上位に表示させたいかというと…ひとまず大手のサイトを優遇しておけば無難であることは間違いありません。
こうした背景もあってか、最近では大企業や業界大手のメディアが優遇して上位表示されるケースが特に目立っていました。
しかし、大手優遇は良いことばかりではありません。特にここ最近は過度な大手優遇により、コンテンツの質が伴っていない場合でも、コンテンツの質で上回っている中小メディアよりも上位表示が容易な状態が恒常化していました。
またそれを逆手に取って、一部上場企業のドメイン配下に無関係のコンテンツを作成する手法や、大手サーバー会社の初期ドメインのサブドメインにサイトを乗せ換える手法で検索結果がハックされるようになりました。
そうなると真面目にコンテンツを作っても意味がないということに多くのWEBマスターや運営担当者が気がつくようになり、長期的に見て検索品質の悪化は免れません。
実際にアップデートの度に個人や中小のサイトは検索結果に表示されづらくなり、更新が停止したりサイトそのものを削除したりと、WEBサイト運営から撤退する個人や企業が続出しています。
こうした状況も鑑みてか、今度のアップデートではドメインパワーの恩恵を過剰に受けていたと見えるサイトの順位が下落傾向に。
ドメインパワー偏重の評価からコンテンツの評価へとやや揺り戻しが起こったように見えます。
この傾向は日本のみならず海外でも同様の傾向となっていて、AmazonやPinterestをはじめとする誰もが知っている規模のWEBサイトでもトラフィックが減少しています。
※参考:PathInteractive
個人ブログの復権
大手ドメインの順位が下落したことで、ランキングの枠に空きができた状態になりました。
そこへ個人の運営するブログやサイトが食い込んでくるようになったのも今回のアップデートの特徴でしょう。
SEOは椅子取りゲームなので下落したサイトがあれば代わりに上がってくるサイトがあるわけですが、最近は大手Aのサイトが落ちても変わりに上がってくるのは大手B、大手Bが落ちたら大手C…といったように大手同士の椅子の取り合いで、ドメインが評価されていない中小のサイトは椅子取りゲームへ参加する資格すらありませんでした。
しかし今回のアップデートでは大手が下落したクエリで個人のブログサイトが上位に表示されているケースも多く見られ、サイト全体でのトラフィックも2020年5月のアップデート以前の水準に復調しているサイトが多数あります。
こうした結果からも、ドメインパワーだけではなくコンテンツの中身も評価指標として重要度が増したと言えるでしょう。
事業会社・事業者サイトは好調
また事業会社や事業者が運営するサイトは変わらず好調です。
事業会社(事業者)運営のサイト…といっても漠然としていて想像がつきづらいかもしれませんが、たとえばポケットWi-Fiをレンタル・販売する事業者が運営するネット回線に関するメディアだったり、家具屋が運営するインテリアのメディアだったり。自社運営のオウンドメディアに近いイメージです。
事業と密接に関連するメディアは以前から評価されやすい傾向にありますが、今回もその傾向は変わらずといったところ。実体性が重視されているとも言えるでしょう。
今後の対策・方針
上記の傾向を踏まえて、今後のSEO施策はどのような対策を考えていけば良いのでしょうか。ポイントを解説していきます。
コンテンツの質を高める
まずは何がなくともこれ、『コンテンツの質』です。
コンテンツの質は今回のアップデート以前から当然に重要ではありましたが、ここ最近は質の高いコンテンツを作っていてもまずドメインパワーによって一定の閾値を超えないと勝負の土俵にすら上がれない…という状況が多くありました。
それが今回のアップデートによりある程度是正され、大手のドメインを借りて内容の薄いコンテンツを量産していたサイトや、サブドメインで運営されていた関連性の低いサイトの順位が下落したことで再びコンテンツが適切に評価されるタイミングに入りましたから、一層コンテンツの充実には力を入れていきたいところです。
専門性・権威性の獲得を意識する
また、サイトの専門性や権威性も意識していきたい要素です。
Googleは検索品質評価ガイドライン内で、ページの品質を評価する上ではE-A-Tが最重要であると述べています。
※参考:検索品質評価ガイドライン(全文英語)
E-A-Tとは『Expertise(専門性)』、『Authoritativeness(権威性)』、『 Trustworthiness(信頼性)』の頭文字を取ったもの。E-A-Tを高い基準で満たすサイトのコンテンツは評価が高くなるということです。
信頼性については先にも述べているとおりですが、同様に専門性や権威性を高めていくことも考えていきましょう。
実際に今回のアップデートでも順位が上昇しているのは何かに特化した個人ブログや企業ブログなどその規模に関係なく、特化サイト・専門的なサイトが多いです。反対に雑記サイトは今回のアップデートで恩恵を受けづらかった印象があります。
大手ドメインの力を借りて上位表示していたサイトが多く下落し、事業会社の運営するサイトが好調なのもこの専門性や権威性といった部分が重視されているからと推測できます。
では具体的にどのように専門性や権威性を高めていけば良いか?ということに関して絶対の答えはないのですが、結局はさきほどのコンテンツの質の追求に繋がってくるでしょう。
サイト内のコンテンツを充実させ情報を過不足なく網羅していけば専門性は強くなりますし、情報を求めているユーザーに認められるサイトになります。そうして「このジャンルならこのサイト」という認知を獲得できるまでに成長すれば権威性も増していく…というイメージです。
ですからやるべきこととしては大きく変わらないのですが、コンテンツを作成する際には、「このキーワードで検索してくるユーザーにとって自社のサイトが一番役に立つ!価値を提供できる!」と自信を持って言えるコンテンツを目指しましょう。
そうすれば自然とE-A-Tを高水準で満たす良質なサイトが出来上がるはずです。
質の高いリンクの獲得を目指す
コンテンツの評価が見直されたとはいえ、リンクという要素も無視はできません。
そもそも学術論文の仕組み(たくさんの論文に参照・引用される論文は価値の高い論文であるという考え)を参考に作られたGoogleにおいて、リンクによる評価決定はGoogleの根幹を成すものであり、その重みづけは時代により変わっても評価指標として重要であることはGoogle誕生から2020年の今まで変わっていません。
GoogleによるWEBサイトの評価指標は無数にあるようにも思えますが、それも大きく分ければリンク(サイト外部からの評価)×コンテンツ(サイト内部の評価)の2大要素によって決定されていることはいまだに揺るぎない事実です。
ただひと昔前と変わったと言えば、ただリンクが大量に付いていれば良いというわけではなく、質の高いリンクが求められるようになったことでしょう。
インターネット黎明期から2010年代前半まではリンクSEOの最盛期であり、スパム的なリンクでもとにかく大量に付いていれば高評価を獲得できる、という時代がありました。
しかし時代が変わりリンクの評価が弱まり、スパムが排除されるようなってからはただリンクが付いているだけでは駄目で、リンクの中身や内容まで見られるようになりました。
今回のアップデートで関連性の薄いサブドメインサイトが下落したことや、個人でも専門的なブログが評価されていること、事業会社のSEOが変わらず好調なことの要因としては、リンク評価の見直しもあるでしょう。
専門的なブログや事業会社のサイトは関連あるサイトからのリンクを受けやすく、結果としてそれが先の専門性や権威性、信頼性を高めることに寄与します。
ですから、E-A-Tを満たすためには高品質なコンテンツ作りと同時に、高品質なリンクの獲得も意識的に行うと良いでしょう。
黙っていても引用される(リンクが張られる)のが理想的ではありますが、その領域まで到達するのは相当の時間がかかりますし、リンクはどこかの誰かに知らずに張られるのをただじっと待っていなければいけない、というルールもありません(もちろんスパム的行為は厳禁ですが)。
“待ちの姿勢”ではなく“攻めの姿勢”で、リンク獲得に動くのも有効なSEO対策のひとつです。
2020年12月コアアップデートの傾向と対策まとめ
2020年12月に実施されたコアアルゴリズムアップデート(December 2020 Core Update)の傾向と対策についてまとめてきました。
今回のアップデートは多くのWEBサイト運営者にとっては追い風となったアップデートではないでしょうか。
やるべきことはコンテンツの質を高め、同時に質の高い(関連性の強い)リンクを獲得する、というこれまでとなんら変わらない内容ですが、ここ最近は「やるべきことをやっても評価されない(大手のドメインパワーによって駆逐される)…」という不遇の時代が続きましたので、その傾向が変わった点で概ね良いアップデートだったと言えるでしょう。
堅実に運営を行えば正しく評価される可能性が以前よりも広がったところで、これを機に今一度所有するメディアのSEOの再構築を考えても良いかもしれません。